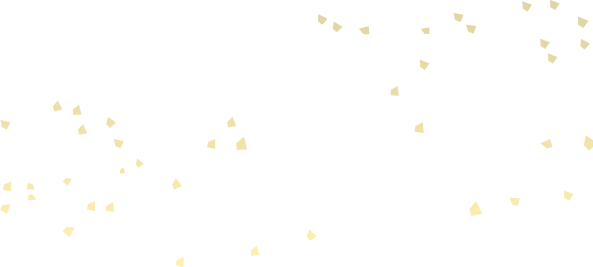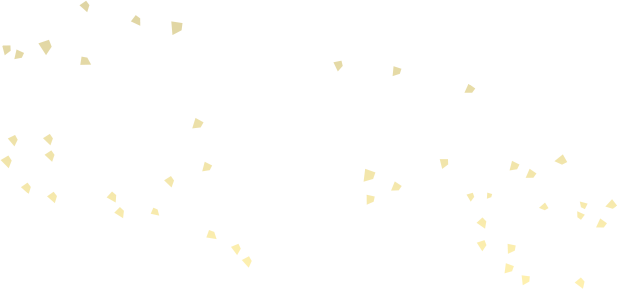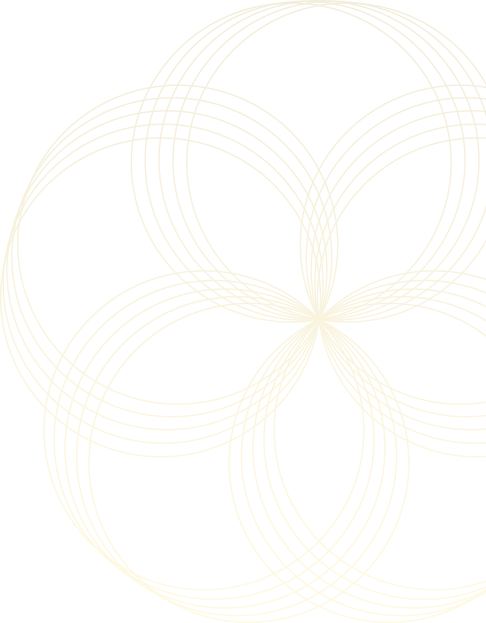家族の笑顔を守るために──「遺言書」の大切な役割
「相続トラブル」という言葉、最近よく耳にしませんか?
実は、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の調停件数は、2000年には約8,900件だったのに、2023年にはなんと約13,800件にまで増えているんです。
背景には、日本が超高齢社会を迎え、相続の件数そのものが増えているという事情があります。
残された家族が“もめてしまう”ことほど、つらいものはありません。心も体も消耗してしまいます。
そのトラブルを未然に防ぐカギになるのが 「遺言書」 です。
「遺言書」と「遺書」の違いって?
似ている言葉ですが、大きな違いがあります。
遺言書 … 法律的に効力がある文書。財産を「誰に、どのように分けるか」を決められる。
遺書 … 気持ちを伝える手紙。法的な効力はない。
遺言書は決まった形式で書かないと無効になってしまうため、注意が必要です。
遺言書が力を発揮する場面
例えばこんなケースです。
不動産など「分けにくい財産」があるとき
法定相続人以外(例:お世話をしてくれた義理の娘)に残したいものがあるとき
相続人がいない、もしくは行方不明の人がいるとき
「私には関係ない」と思っていても、実は多くの人に関わるテーマなんです。
遺言書には2つの種類があります
自筆証書遺言 … 自分で気軽に書けるけれど、なくしたり無効になるリスクがある。
公正証書遺言 … 公証役場で作り、専門家も関与するので安心度が高い。
状況や家族構成に合わせて選ぶことが大切ですね。
遺言書がもたらす安心
遺言書があると、
家族が争わずにすむ
相続の手続きがスムーズになる
という大きなメリットがあります。
さらに、遺言書には「付言事項」といって、財産分けとは別に自分の思いを残すこともできます。
「これまでありがとう」や「この財産を大切にしてね」といった一言が添えられると、単なる法的な書類ではなく、家族の心に残るメッセージになります。
✅ まとめと行動のヒント
遺言書は「財産の分け方」を決めるだけでなく、残された家族の笑顔を守るための準備でもあります。
「まだ早いかな」と思う時こそ、元気なうちに考えておくことが大切です。
もし「うちの場合はどうしたらいいんだろう?」と少しでも気になったら、専門家に相談してみるのがおすすめです。法律の知識がなくても、専門家に話すことで、自分に合った方法を見つけやすくなります。
未来の安心のために、まずは小さな一歩を踏み出してみませんか?